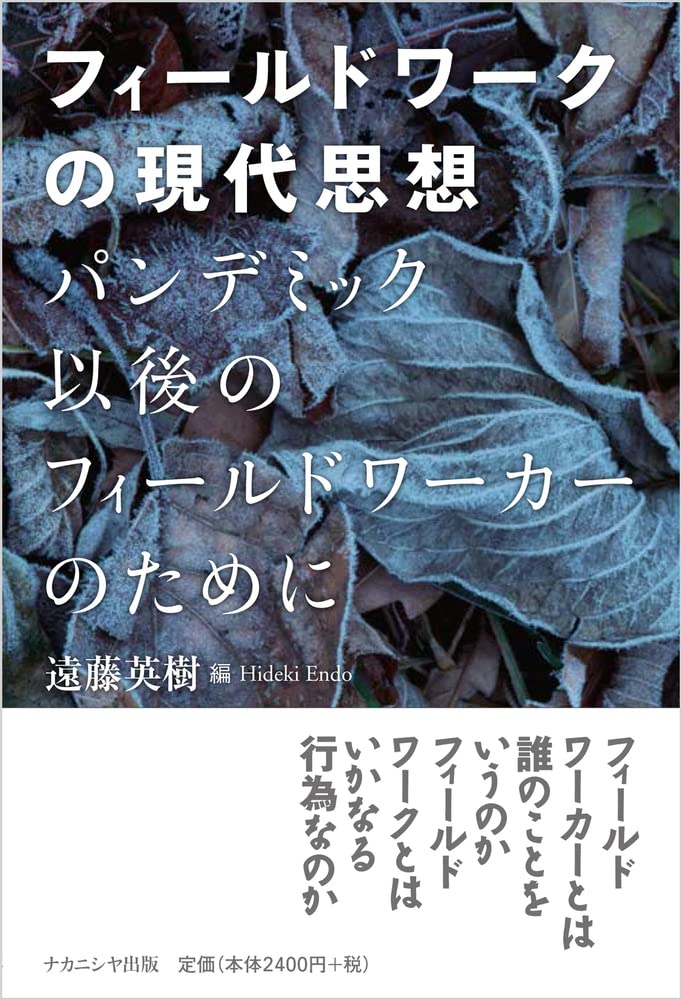
フィールドワークの現代思想:パンデミック以後のフィールドワーカーのために
社会学・人類学・地理学分野の14名が、自身の研究に必須の営みである「フィールドワーク」について、誰が、何のために、何を、どのように行う実践なのかを問い直し、その意義や問題や可能性を考究する。

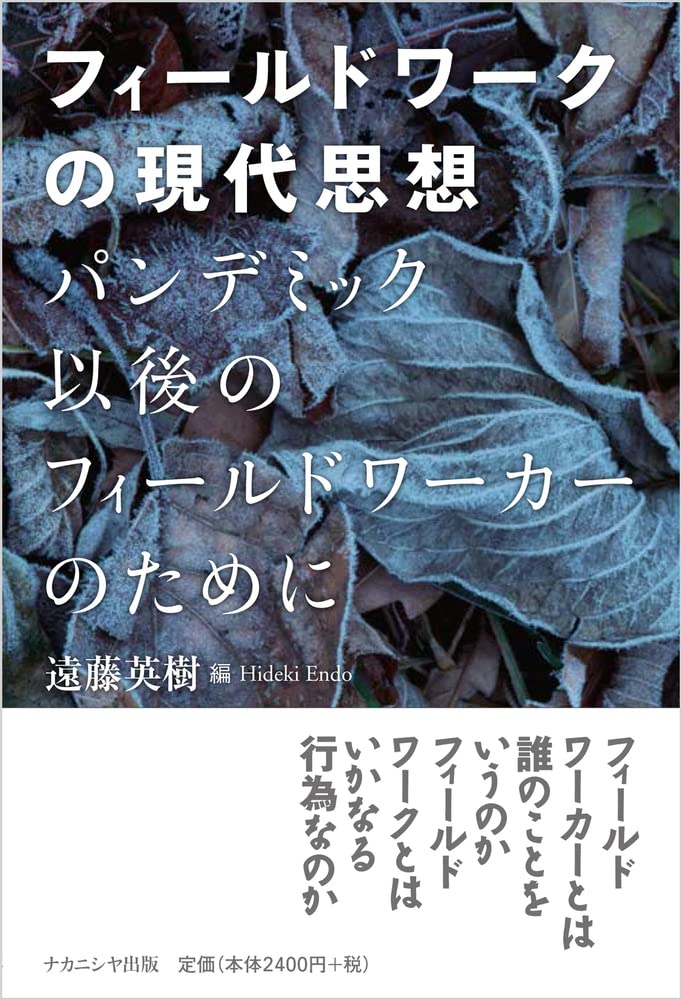
社会学・人類学・地理学分野の14名が、自身の研究に必須の営みである「フィールドワーク」について、誰が、何のために、何を、どのように行う実践なのかを問い直し、その意義や問題や可能性を考究する。

アジア14か国のリプロダクション調査の成果をまとめたもの。テクノロジーの利用から、妊娠出産、家族計画、人工妊娠中絶、産後の養生の現在まで、変容するアジアの出産の最前線を捉える。
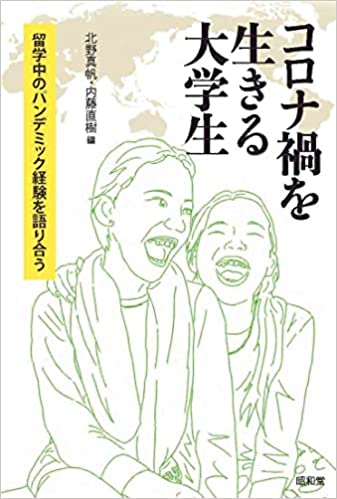
新型コロナウイルス感染症が問題化されつつあった2020年初頭に世界各地に留学していた大学生が、人類学者6名との対話を通じて、当時の混乱のなかで感じた違和感や葛藤を綴ったオートエスノグラフィです。

文化人類学・哲学・心理学等の専門家による新たな学術領域「顔・身体学」の論集です。海外フィールドワークや対面での実験ができなくなった経験にも触発されて編まれました。
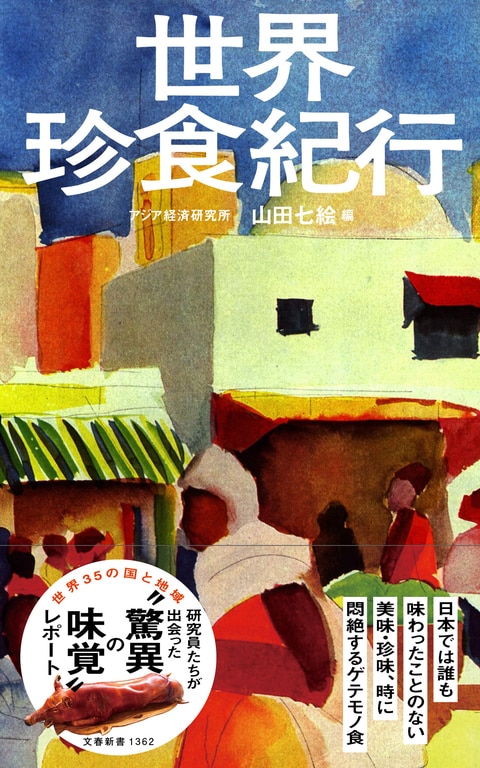
アジア経済研究所の総勢37名の開発途上国の専門家が、35の国・地域の食について思う存分語ったエッセー集です。研究員たちの世界各地での衝撃的な食体験を通して、その地域の社会・文化がより深く見えてきます。
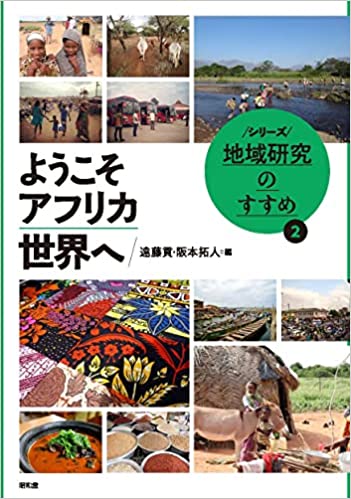
自然、生活、世界観、歴史、政治、経済、移民・難民、感染症、教育、国際関係など遠くて近いアフリカを多面的に学ぶ入門書。
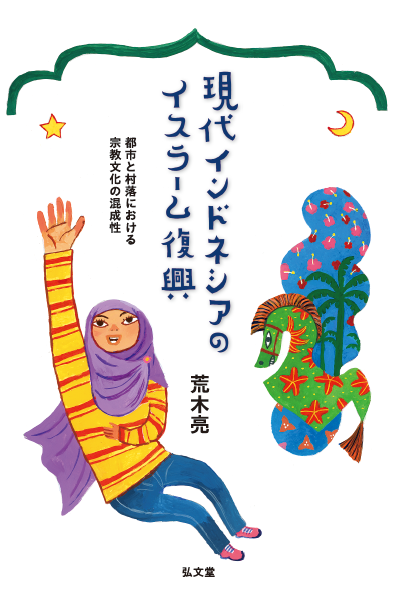
インドネシアは世界最大2億3000万人のムスリムが暮らすイスラーム大国です。現地のイスラーム復興とその独特な動態を「構造主義」と「混成性」をキーワードに生活世界の日常性から紐解きます。
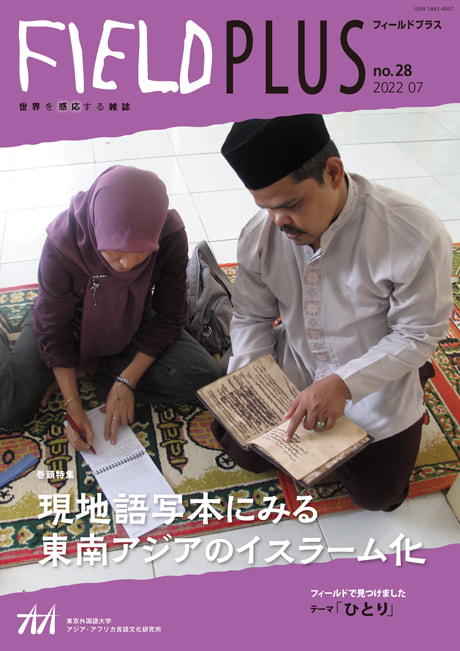
東京外国語大学AA研の雑誌『フィールドプラス』28号が2022年7月10日に刊行されます。巻頭特集「現地語写本にみる東南アジアのイスラーム化」ほか、フィールドにまつわる記事満載です。
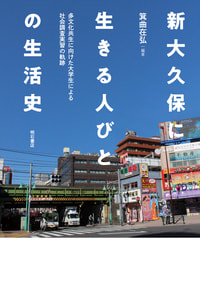
多国籍の街新大久保の現在を、当地に生きる外国にルーツをもつ人びとの語りから描き出した。大学の社会調査実習の成果をまとめたものでもあり、実際の授業内容等も紹介されているユニークな一冊。
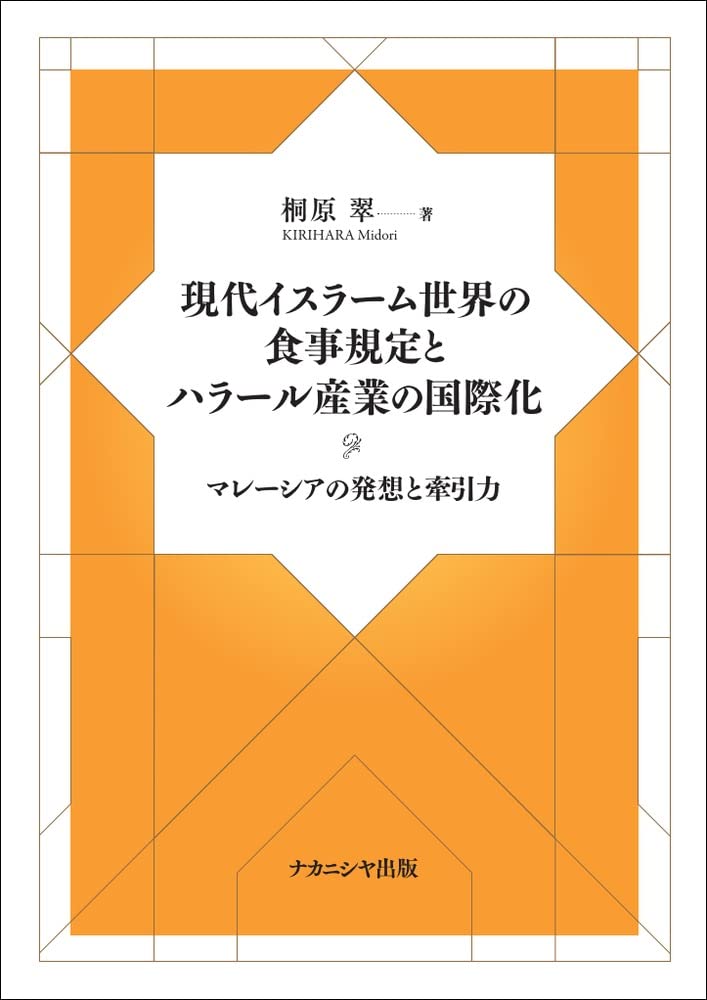
現代を生きるムスリムの食事規範の動態を、ハラール産業先進国マレーシアを事例に描く。文献調査に加えてフィールド調査を行うことで、認証制度と日常生活、ローカルとグローバルの関係性の複雑さが明らかになる。