
神奈川大学人間科学部 専任教員公募(3件)「地理学」、「地域研究」他

Fieldnetでは、フィールドワークの手法やフィールドワークに基づいた
研究成果に関する情報を募集しています


本特別展では人類史的視点をふまえながら、アジアやオセアニアの海域世界における多様な舟を紹介します。関連イベントも開催されます。

国際学校保健の歴史的変遷をたどりながら、日本や海外の開発パートナーの国際協力活動や、学術的研究の最新動向について学ぶセミナーです。ふるってご参加ください!


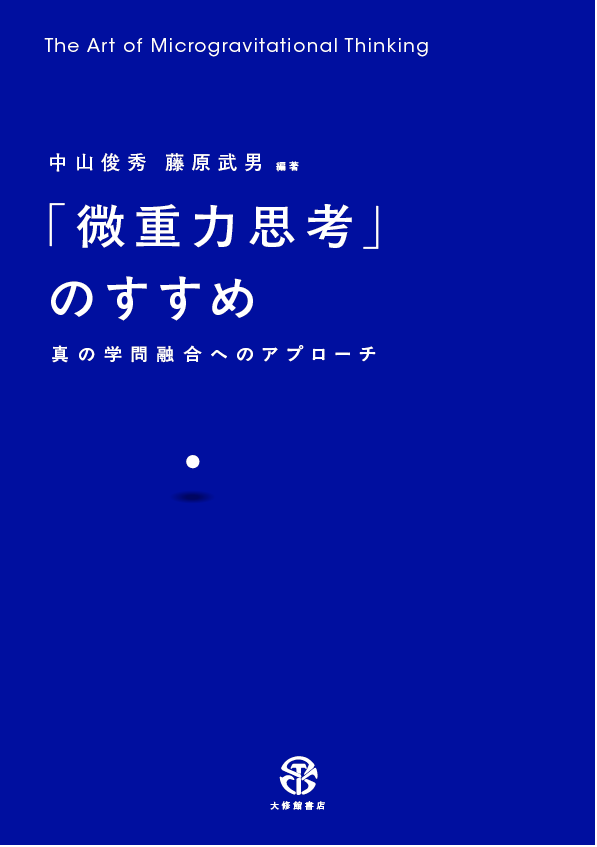
本書は、新型コロナウイルス感染症対策をケーススタディに、異分野の専門家が専門の壁を越えた対話と解決策の共創を目指して重ねた実践的共同研究活動から生み出された対話法の提案です。


アジア・太平洋戦争終結80年を迎えた今年、写真展やギャラリートークを通じて、「戦後」の現実と向き合い続けてきた生活者の思想的営為の記憶とその現在について考えます。


これからの時代に里山里海をどう活かしていくのか、私たちの暮らしや生物多様性を含め様々な側面から里山里海を学ぶ会として開催します。